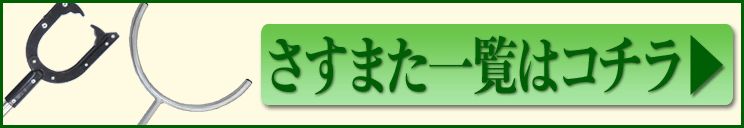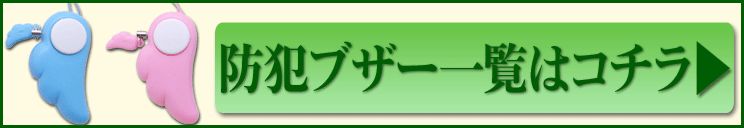子どもが安心な生活を送るためには、日頃から防犯対策が欠かせません。ここでは、当店の取扱い商品からご使用されている防犯用品・防犯グッズについて紹介致します。
さすまた
さすまたは、犯人の確保、押さえつけなどに有効な防犯用品です。現在、さすまた設置の義務付けられている保育園や学校もあり、当店でも納入実績のある防犯用品です。しかし、その効果的な使用方法などについてきちんと理解し設置している学校施設はそう多くありません。
なぜさすまたを使うのか
さすまたは、江戸時代には犯罪者を捕獲する捕り物のための道具の内の一つとされ、日本では古くより捕縛に使う道具として発展してきました。
近年では、2001年に起きた附属池田小事件や不審者などの学校侵入などを契機に、防犯対策、防衛力強化として学校施設などで導入が進められています。
近年では、2001年に起きた附属池田小事件や不審者などの学校侵入などを契機に、防犯対策、防衛力強化として学校施設などで導入が進められています。
学校施設におけるさすまたの事例について
学校施設における地域ぐるみの防犯対策事例集(※1)によると、東京都のT大学付属小学校では、平成18年に防犯対策強化のためさすまたを導入しました。また、高知県四万十市立N小学校では、夜間等に校内へ不審者が侵入する事件が発生したことをきっかけに対応策を検討し、さすまたを防犯設備の一つとして校舎内に設置しています。
そして、学校の安全管理の取組状況に関する調査(平成21年度実績)(※2)内の学校の安全管理の体制の整備の状況によると、さすまたは全国で85.2%普及しており3万校以上の学校施設で普及しています。今やさすまたによる防犯対策は必要不可欠といえるのではないでしょうか。
そして、学校の安全管理の取組状況に関する調査(平成21年度実績)(※2)内の学校の安全管理の体制の整備の状況によると、さすまたは全国で85.2%普及しており3万校以上の学校施設で普及しています。今やさすまたによる防犯対策は必要不可欠といえるのではないでしょうか。
特性と効果的な使用について
一般的なさすまたは、犯人を押さえつけるためのU字型パーツと棒が組み合わさったような形をしています。棒を持ち、相手を押さえつければよいのですが、効果的に使用するために一つ覚えておかなければならないことがあります。
それは、使用時に自分と相手がつながっているということです。使用する際に相手の方が強い場合、さすまたを押し返されたり奪われる可能性があります。そのため、効果的に使用するには複数人で複数本のさすまたを使用してください。万が一、複数人・複数本での使用が難しい場合は、相手を捕獲することはあきらめ、相手の首付近に構えて威嚇にとどめましょう。ただし、いずれの場合も無理に行動してはいけません。危険な状況から抜け出すということを第一に考えてください。
また、通常のさすまたに加えて足用のさすまたをサブに使用することも効果的です。足用のさすまたには、「返し」がついており一度足を入れたら容易に外せません。このため、相手の動きを制限することができ、非常に効果的です。しかし特性上、足用のさすまたは単体での使用が難しい防犯用品です。そこで、複数人での使用が想定される環境で、通常のさすまたとの併用し設置することが望ましいです。
それは、使用時に自分と相手がつながっているということです。使用する際に相手の方が強い場合、さすまたを押し返されたり奪われる可能性があります。そのため、効果的に使用するには複数人で複数本のさすまたを使用してください。万が一、複数人・複数本での使用が難しい場合は、相手を捕獲することはあきらめ、相手の首付近に構えて威嚇にとどめましょう。ただし、いずれの場合も無理に行動してはいけません。危険な状況から抜け出すということを第一に考えてください。
また、通常のさすまたに加えて足用のさすまたをサブに使用することも効果的です。足用のさすまたには、「返し」がついており一度足を入れたら容易に外せません。このため、相手の動きを制限することができ、非常に効果的です。しかし特性上、足用のさすまたは単体での使用が難しい防犯用品です。そこで、複数人での使用が想定される環境で、通常のさすまたとの併用し設置することが望ましいです。
さすまたの必要性
学校施設で使用が想定されるケースは、教室や廊下、職員室など幅広くあります。相手が凶器(ナイフなど)を持っている可能性も考えられます。武器を持っている相手に対し近づくのは危険です。しかし、さすまたは相手から離れて使用することができ安全に対応することが可能です。また、複数人・複数本で使用することで、より強力な防犯対策にもなります。
防犯ブザー
防犯ブザーは、非常時にピンを引くと大音量のブザーが鳴り、危険を知らせてくれる防犯グッズです。現在、児童や生徒の登下校中の犯罪防止などから、多くの学校施設で防犯ブザーが普及しています。しかし、効果的な使用にはいくつか注意点が必要な防犯用品になります。
一つめに、音の大きさです。防犯ブザーによっては、生活音が多い場所などでの使用時にブザー音を認識してもらえず防犯効果が薄い場合があるためです。具体的には、90dB(デシベル)以上出るものが望ましいです。
二つ目に電池切れや商品の劣化です。普段鳴らさない商品のため電池切れや、毎日通学に使用するランドセルやバックなどに着けるためなかなか商品の劣化に気付かず、いざという時に使用できないといったケースもあるようです。そのため、電池切れや劣化があるかきちんと日々の点検、確認することが必要です。
一つめに、音の大きさです。防犯ブザーによっては、生活音が多い場所などでの使用時にブザー音を認識してもらえず防犯効果が薄い場合があるためです。具体的には、90dB(デシベル)以上出るものが望ましいです。
二つ目に電池切れや商品の劣化です。普段鳴らさない商品のため電池切れや、毎日通学に使用するランドセルやバックなどに着けるためなかなか商品の劣化に気付かず、いざという時に使用できないといったケースもあるようです。そのため、電池切れや劣化があるかきちんと日々の点検、確認することが必要です。
学校施設における防犯ブザーの配布・貸与について
学校の安全管理の取組状況に関する調査(平成21年度実績)(※2)内の防犯ブザー(防犯ベル)の子どもへの配布(又は貸与)を行っている学校の調査では、全国の学校で約44.6%と半数以下であり、学校施設全体における防犯ブザーの配布や貸与はあまり普及していません。内訳を見ますと、小学校では約84.6%と非常に高い割合ですが、中学校や高等学校などの学校施設では30%にも満たない非常に低い値です。
防犯ブザーの電池切れ、劣化などを考えますと小学校だけでなく中学校や高等学校などでも防犯対策として防犯ブザーの配布・貸与を行うことでより安心安全な学校生活につながるのではないでしょうか。
防犯ブザーの電池切れ、劣化などを考えますと小学校だけでなく中学校や高等学校などでも防犯対策として防犯ブザーの配布・貸与を行うことでより安心安全な学校生活につながるのではないでしょうか。
防犯ブザーの必要性
不審者は、「〇〇(子どもの好きなもの)を買ってあげるからついてきてよ。」「道に迷っているから教えてほしい。」「お母さんが倒れたんだ。急いで病院に行こう!」など様々な手口で近づいてきます。まず、そうした声かけをされたときについていかないということが大切です。
また、不審な人物から声かけをされた際は、必ず一定の距離をあけることが大切です。それでも、近づいてきたり、襲い掛かろうとしたときに、防犯ブザーを使用してください。防犯ブザーを使用後は防犯ブザーを持ったままでなく、人通り多いところなどに逃げることが重要です。
防犯ブザーを持つことで、音で周囲の住民に危険を知らせるだけでなく、犯人が犯罪に気づかれるのを恐れ逃げることもあり、犯罪を未然に防ぐ効果が期待できます。
また、不審な人物から声かけをされた際は、必ず一定の距離をあけることが大切です。それでも、近づいてきたり、襲い掛かろうとしたときに、防犯ブザーを使用してください。防犯ブザーを使用後は防犯ブザーを持ったままでなく、人通り多いところなどに逃げることが重要です。
防犯ブザーを持つことで、音で周囲の住民に危険を知らせるだけでなく、犯人が犯罪に気づかれるのを恐れ逃げることもあり、犯罪を未然に防ぐ効果が期待できます。
お見積りやご注文などのお問い合わせ
参考文献
※1 出典:学校施設における地域ぐるみの防犯対策事例集 文部科学省大臣官房文教施設企画部 国立教育政策研究所文教施設研究センター(http://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div11-shisetsu.html)
※2 出典:学校の安全管理の取組状況 文部科学省(http://www.mext.go.jp/)
※2 出典:学校の安全管理の取組状況 文部科学省(http://www.mext.go.jp/)